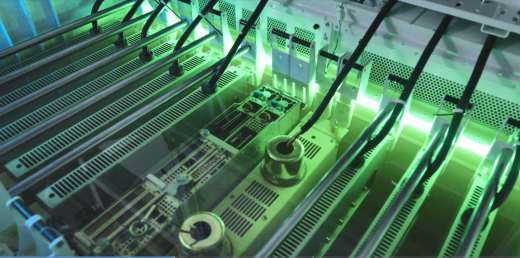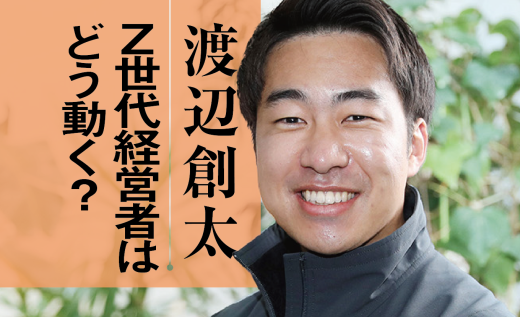人生そのものを支える――!厚労、経産連携で切り拓く介護新時代とは
日本は世界に類を見ない超高齢社会を迎えている。
高齢者のニーズに細やかに対応していくためには、公的介護保険制度をしっかり維持していくとともに、保険外の民間サービスの充実も欠かせない。介護に関する、社会的機運の醸成や職場・地域のサポートも重要だ。
介護する人、介護される人、多様なニーズが存在するなか、行政の役割、地域社会・企業に求められるものとは――。それぞれの立場で、これからの介護の在り方を模索する厚生労働省認知症施策・地域介護推進課の和田幸典課長と経済産業省ヘルスケア産業課の橋本泰輔課長に話を聞いた。
多様化する高齢者像。「総合事業」で新しい介護を目指す
――介護に関する施策の現状はどうなっていますか。
和田 私は介護保険、高齢者福祉に関わることを担当しています。その大きな柱が「地域包括ケアシステム」の構築です。
介護が必要な高齢者には、介護保険の仕組みの中でサービスを提供していくことが基本になります。その上で、介護保険のサービスにとどまらず、高齢者の福祉、生活をどう守っていくかが、今大きな課題となっています。
団塊の世代の方々が75歳を迎える時期が近づいています。従来の介護保険サービスの重要性を否定するものではありませんが、この世代の高齢者像を考えると、それにとどまらないサービスが必要とされていると実感しています。若い頃に楽しんでいた趣味なども多様です。そういった視点も含めて、いろいろとサービスの選択肢を増やしていかなければいけない。
そのための制度的な仕組みの一つが、「介護予防・日常生活支援総合事業」です。税と社会保障一体改革の中で、介護保険給付の中から「要支援」の方への訪問介護や通所介護を移行した事業で、ボランティア、NPO、近年話題になっている高齢者自らが生活支援の担い手となるなど、様々な形で介護予防・生活支援サービスを提供するとともに、高齢者の社会参加を同時に進めていくという制度的意図を持った挑戦的な仕組みです。

厚生労働省認知症施策・地域介護推進課の和田幸典課長。「介護保険のサービスにとどまらず、高齢者の福祉、生活をどう守っていくかが、今大きな課題となっています」
ビジネスケアラーへの支援は不可避。現場の課題は多様化する高齢者ニーズへの対応策
橋本 介護に関しては、介護保険制度を核にして進められています。私たちの問題意識としては、高齢化が進み、高齢者ニーズも多様化している中で、介護保険サービスだけで全てを賄っていくのは、非常に難しくなっているということです。
仕事をしながら介護をしているビジネスケアラーやワーキングケアラーと呼ばれる人たちが非常に増えています。現在すでに260万人以上と推定されており、2030年には300万人を超えると予想されます。それによる経済損失を試算すると9兆円を超え、社会全体として対策すべき課題だと考えています。
我々としては、高齢者本人や、介護する側であるビジネスケアラーにとって、介護保険でカバーできないニーズに対応できるような保険外サービスというものを、しっかりと創出していかなければならない。そういった問題意識で取り組んでおり、これは介護予防・日常生活支援総合事業の考え方とも一致するところがあります。厚生労働省と連携して、今後も進めていきたいと思っています。
――介護に関する施策を進めていくうえで都市部や地方での課題は何でしょう。
和田 都市においても、地方においても最大の課題は介護に関わるサービスでの人手不足だと思います。介護サービスの拡大、多様化を図っていくため、我々としては介護の仕事の魅力もあわせて発信していかなければなりません。介護保険の仕組みの中では、都市であろうと地方であろうと地域を問わず、必要なサービスを提供していくことが、我々の責任だと思います。
他方、人手不足という課題にどのように対処していくか。都市と地方では、それぞれ違う解決策があるのではないかと考えています。
橋本 介護は、画一的な対策には向きません。特に保険外サービスに焦点を当てると、その地域の企業など現存のプレーヤーに、いかに高齢者向けサービスに参入してもらうかが重要ですが、地域によって事情が異なり、地域特性に応じたサービスが求められています。

経済産業省ヘルスケア産業課の橋本泰輔課長。「介護保険でカバーできないニーズに対応できるような保険外サービスを、しっかりと創出していかなければならない」
カギを握る民間企業の介護関連サービス参入。都道府県との連携も重要
――民間企業の介護分野への参入に関してクリアすべき課題はなんですか。
橋本 地域の事業者には、介護をめぐる課題について認識し、それに対するサービスの提供主体になってもらわなければいけません。一方で、事業者としては、一定の事業継続性を生み出していく必要があります。様々なニーズへ実際にマッチするものを、どう繋げていくかが重要です。
一つの市町村だけで、求められているサービスを特定してつくり上げていくのは現実的には難しい。サービスを模索する市町村と、それを俯瞰して見ることができる都道府県との連携が必要になってくると思います。
和田 2023年に開催した「介護予防・日常生活支援総合事業の充実に向けた検討会」の中で、我々も民間事業者からヒアリングをし、様々な課題を伺いました。
「現状のサービスの対象者が少ないならば、高齢者が要介護に至るまでの長い道のりの中で、そのサービスがどう関わっていけるかという視点を持てば、新たに見えてくるものがあるのではないか」とか、「市町村だけでプロデュースするのが難しいのであれば、都道府県の圏域ならばどのようにサービスをつくれるかという視点が必要だ」など、重要な指摘をいただきました。
事業としての持続可能性が課題。認知症、単身高齢者など新たな課題も
――多様化する介護ニーズには、どのようなものがあるのでしょうか。
橋本 ビジネスケアラーにとっては、買い物、移動や食事の用意、掃除など家事全般が負担となっています。これまでの人生の経緯の中で、やりたいことも人それぞれあります。いわゆる生活支援というところを超えて、介護する側、介護される側の人生そのものをどう支えるのかという視点が必要だと思います。
企業からすれば、そこに一つのビジネスチャンスがあります。ビジネスモデルを、いかに持続可能なものにしていくかが課題です。
和田 介護保険が抱える、新しくかつ大きな課題が二つあると思います。
一つは認知症です。認知症の高齢者が増えるにつれ、生活上の課題や医療関係を含む新しい課題がたくさん出てきています。もう一つは、身寄りのない高齢者が増えているという問題です。身寄りがないというと、貧困高齢者をイメージしがちですが、資産がある方、ない方も様々いらっしゃいます。そうした方々の意思決定を支援しながら、必要なサービスにつなげていかなければいけません。
この二つは従来の介護保険制度だけではカバーしきれない、新しい課題です。
官民連携で新しいサービス生み出す。求められるデザイン力、プロデュース力
――自治体と企業などの連携がうまくいっている事例はありますか。
橋本 愛知県豊明市では、地域ケア会議という福祉関係者が地域の介護に関する問題を共有する場へ、地域の民間事業者も巻き込み、様々なソリューションを実現しています。地域のスーパーと連携して、買い物はできるが買ったものを家に持ち帰るのが難しい方を対象に、購入した商品を当日無料で配送するサービスを実施したり、自動車メーカーと連携し、地域のスポンサーを得て移動を安価に提供するサービスを展開したりしています。
また、今、民間の取り組みとして介護関連サービスの業界団体が設立されつつあります。その中でガイドラインがつくられ、そのガイドラインを遵守している企業を認証し、社会へ明示していくことで、よりサービスへの信頼性が高まると期待しています。
和田 我々も市町村に対して、地域の事情に応じた総合事業のデザイン力、プロデュース力を高めることを期待しています。そこはぜひ経済産業省の取り組みとも連携して、良い事例を生み出していきたいです。

認知症、単身高齢者が新たな課題だと指摘する和田課長
待ったなしの認知症対策。「当事者参画型開発」で進める社会全体の理解
――先ほど少し触れられましたが認知症施策についてのこれからは。
和田 2024年はまさに「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」(認知症基本法)が施行された重要な年です。認知症の方本人の意思を尊重することがこの法律の基本に据えられており、これに基づいて地域づくりを進めていくことになります。これは介護保険だけでは対応できません。どのようなサービスをつくっていくか、地域づくり、社会づくりの観点まで広げる必要があります。
橋本 経済産業省は「オレンジイノベーション・プロジェクト」を進めています。その重要な柱が「当事者参画型開発」の推進です。企業の製品・サービス開発の現場に認知症の当事者に深くコミットしてもらい、ただ単に開発のヒントをもらうだけではなく、一緒につくりあげていくものです。
すでに、「当事者参画型開発」によって、認知症の方のための見守りサービスや認知症の方にも操作しやすいガスコンロなどが誕生しています。こうした製品・サービス開発の考え方を、更に広げていく方針です。
認知症の方は年々増えており、ニーズは間違いなくあります。事業として成り立つかどうかという観点もありますが、企業のブランディングとしての効果も大いにあると思います。社会にアピールし、企業の取り組みが評価される環境が大事だと思っており、経済産業省としては、その点をしっかりと発信していきたいと考えています。
▶関連記事:政策特集 拡張する介護領域 vol.3 認知症とともに歩む!オレンジイノベーション・プロジェクトが目指す共生社会とは

介護はみんなで対処すべきだという共通理解を広げたいと強調する橋本課長
和田 認知症の方本人に入ってもらって商品開発をすると、意外な気づきや、いろんな改良点が見えてきます。そうした小さな改良や商品開発、あるいはマーケティングを進めていくことは、これからの企業にとってビジネスチャンスになり得ます。認知症を基点に、地域社会をつくっていくことが、厚生労働省ひいては政府全体の地域づくりの基本になると思います。
「オープンに語れる場」づくりが重要。ゴールは「国民の幸福」
――最後に介護政策の今後について。
和田 介護についての課題をオープンに語れる場をつくることは非常に重要だと思いますし、それは厚生労働省だけではできません。経済産業省の力も借りて一緒に出来ればと思います。連携することで新しいニーズに対するサービスをつくり出せると期待しています。
橋本 政策の最終的なゴールは国民の幸福、最近流行りの言葉で言うとウェルビーイングです。今、介護を「個人の課題」から「みんなの話題」にしていきたいと、「OPEN CARE PROJECT」を進めています。介護についてみんなで話題にして、みんなで対処すべきものだという共通理解を広げたい。そういう社会機運を醸成したいと思います。
介護を取り巻く様々な課題に、厚生労働省と共に向き合っていきたいと思っています。
▶関連記事:政策特集 拡張する介護領域 vol.1介護を「個人の課題」から「みんなの話題」へ!「OPEN CARE PROJECT」が目指す未来
【関連情報】
「仕事と介護の両立支援に関する経営者向けガイドライン」について(METI/経済産業省)
オレンジイノベーション・プロジェクト~認知症当事者とつくる、誰もが生きやすい社会~(METI/経済産業省)
※本特集はこれで終わりです。次回は「好機を逃さない産業立地政策」を特集します。