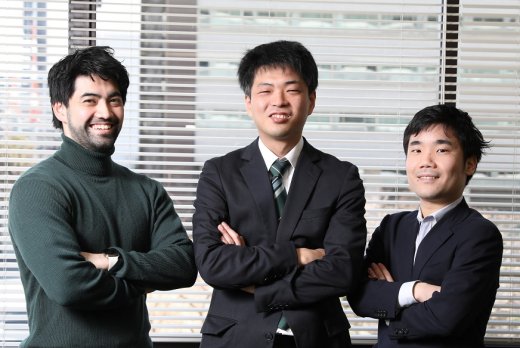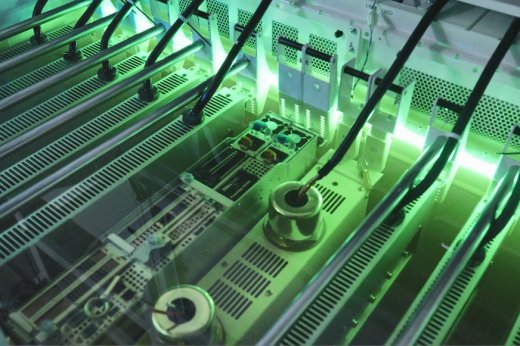
新ブランド続々 顧客開拓に挑む継承者たち

お茶とお菓子で一息つく大切な時間を演出する有田焼の新ブランドはこれまでのイメージを一新している
暮らしを彩る日用品。伝統的な技法を守りつつも、現代のライフスタイルや嗜好(しこう)を捉えた商品開発で、新たな顧客を獲得する産地の動きが広がる。
「大名の日用品」が身近に
江戸時代、門外不出とされた「鍋島焼」。その歴史は、将軍家への献上品を作るため有田・伊万里地域(佐賀県)でえりすぐりの陶工を集めて鍋島藩が藩窯を築いたことにさかのぼる。庶民には手が出なかった「大名の日用品」が、いま身近なものになりつつある。
鍋島藩窯の末裔(まつえい)である「鍋島虎仙窯」が手がける日用品ブランド「KOSEN」は、鍋島焼の伝統的な技法を生かしつつ、現代の暮らしにマッチする商品アイテムを手軽な価格帯で展開している。翡翠のような美しい色合いが目を惹く煎茶椀は、口当たりがよく、スタッキングも可能。重ねることで青竹のようなすがすがしい姿が浮かび上がるよう計算されている。
鍋島焼には、代表的な技法として、藍色の呉須(ごす)で下絵を描き、赤・青・黄で下絵を施す「色鍋島」や天然の青磁原石を用いた青磁釉をかけた「鍋島青磁」などがあるが、前述の茶碗はそのひとつ。番頭兼絵師である川副隆彦さんによると、「窯主だった祖父(川副為雄さん)は、とりわけ青磁の魅力を多くの人に知ってもらい、日常的に使ってもらいたいとの強い思いを持っていました。10年にわたる釉薬研究の果てにこれら商品が生まれました」。川副さんは、新たなブランドを美術品と量産品の中間にある「美術的商工芸品」をコンセプトとし、技法やデザインを分かりやすく伝えることで鍋島焼の魅力を発信したいと語る。

鍋島焼の魅力を語る鍋島虎仙窯の川副隆彦さん
逆転の発想で挑む
有田焼の「渓山窯」の三代目である代表取締役の篠原祐美子さんが、今年発表した器ブランド「mg&gk(もぐとごく)は、器そのもの美しさをめでながら、一息つく大切な時間を演出するアイテムとして打ち出したのが特徴だ。2月に発表した「フィナンシェと紅茶の器」に加え、新たに「ぼうろとほうじ茶の器」を9月に発表したばかり。ブランド名は、こうした「ちょこっと『もぐもぐ、ごくごく』食べたり飲んだりするための器をイメージして名付けている。
白磁に青く発色する呉須を使用した染付や豪華絢爛(けんらん)な色絵で知られる有田焼だが、新ブランドの商品アイテムはいずれも淡く繊細な色づかい。「極限まで色彩を薄くするには、これまでとは正反対の技法が必要で、ある意味、職人さん泣かせでした」(篠原さん)。実際の色合いは、焼き上げてみないと確認できない部分も多く、商品化までは試作品が山積みになったとか。しかし、2019年2月に市場投入したところ、これまで中心だったシニア世代に加え、若い女性を中心とした新たな顧客層をつかみつつあることを実感した。
「モノがあふれている時代だからこそ、日常のひとこまを演出するアイテムや、一見そうは見えないのに、『実は有田焼』という意外性が心をつかむのではないでしょうか」(篠原さん)。「初めは半信半疑だった父も喜んでいます」と語る。

女性ならではの商品開発で顧客を獲得しつつある渓山窯の篠原祐美子さん
産地あげて魅力発信
窯元が作る自社ブランドとは一線を画し、産地をあげた地域ブランド構築に取り組む動きもある。四日市萬古焼(三重県)の窯元である山口陶器が展開する「かもしか道具店」は、スタイリッシュで機能的でありながら、丸みを帯びたどこか愛らしいキッチン用品で人気を集めている。ブランド名の「かもしか」は、三重県のシンボルであるカモシカに由来。山口陶器代表取締役の山口典宏さんは、他にも四つの窯元仲間と立ち上げたテーブルウエアブランド「4th market」を展開するほか、町内全域を教室に見立てた体験型ワークショップを通じて産業観光に取り組むなど、地域振興の中心的存在でもある。

三重県菰野町の町おこしの中心的存在でもある山口陶器の山口典宏さん
そんな山口さんだからこそ、商品開発にあたっては、産地を盛り上げたいとの思いを共有する関係者と作り上げる姿勢を貫く。それは窯元だけではない。写真で手にしている耐熱の陶器製やかんは、持ち手が真ちゅうだが、「これはさすがに地元だけでは無理かと思いつつも、声をかけてみたところ、引き受けてくれる金属加工メーカーがありました。すべて『メイドイン菰野町』です」と胸を張る。
※ 次回は、こうした産地の挑戦を、工芸を生かした生活雑貨の企画製造・販売や経営コンサルティングを通じて後押しする中川政七商店の千石あや社長の話を紹介します。