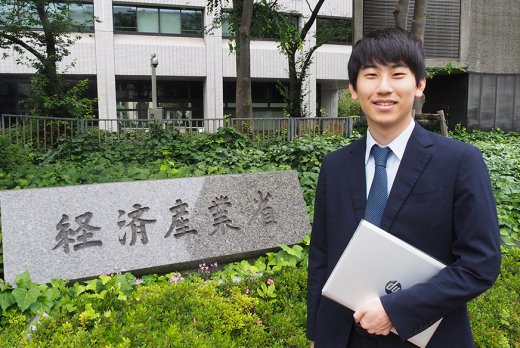”なるほど!”が集まるウェブマガジン
わが町に企業を呼び込め!カギを握る「産業用地」の確保
ロシアのウクライナ侵略、米中対立などの地政学的リスクの高まり、為替相場の円安基調などを背景に、日本企業による生産拠点の国内回帰や国内生産体制強化の動きが活発化している。半導体など海外企業が日本に生産拠点をつくる動きも相次ぐ。
この流れに乗って、企業や工場を誘致することができるかどうか。全国の自治体にとっては、地域経済の今後を左右しかねない重要なテーマだ。
産業立地政策をどのように進めていくか――。今、国や自治体は正念場を迎えている。第1回は、産業立地を進めるうえで重要なカギを握る「産業用地」について考える。
バブル崩壊で開発凍結。不足する産業用地
産業用地の不足は深刻だ。国内の産業用地のストック(分譲可能用地)は過去30年で最小規模となっている。2001年には約18,000ヘクタールあったが、2021年には10,588ヘクタール、2022年には10,096ヘクタールと減少した。
1993年以降の円高を受けて、製造業を中心に、工場などの生産拠点を中国や東南アジアなど国外に移す動きが進み、工業団地は逆風にさらされた。自治体の中には、バブル期に作った団地が売れ残り、整備を「凍結」せざるを得ない状況に追い込まれるなど、苦い経験を味わった。

地域未来投資促進法を活用。手続き緩和でより円滑に
こうした状況を乗り越え、前に進めようと2017年に施行されたのが、「地域未来投資促進法(地域未来法)」だ。
工業団地の開発には一般的に3~6年程度かかるとされる。産業用地の確保に向けた農地転用の手続きなど、関係者との調整には「相当の時間」が必要となるためだ。このため、開発期間が見通せないために企業から敬遠され、自治体が誘致の機会を逸してしまうケースが珍しくなかった。
地域未来法は、農地転用に必要な手続きを大幅に緩和した。
産業用地への転用が原則認められていない第一種農地(農地法)の転用が可能になるほか、市街化調整区域(都市計画法)にあたる土地についても、一定の条件を満たせば、食品関連物流施設・植物工場・データセンターなどの建築を目的とした開発許可が可能になった。
転用不可だった農地に新工場整備。富山県高岡市のケースとは

「地域未来投資促進法」を活用して開発した用地に完成した機械部品メーカーの工場(富山県高岡市)
「今ある工場の隣接地に、新工場用地を開発したい」――。
機械部品メーカーから富山県高岡市に相談があったのは、2017年のことだった。
土地の利用目的は、都市計画法や農地法などで厳しく制限されている。隣地だからといって、すぐに拡幅できるわけではない。このメーカーは、2008年から段階的な工場の拡張を計画していたが、リーマン・ショックなどのあおりで延期。この間、不運にも、新設工場の建設を予定していた土地が、農地法の改正によって、産業用地への転用が可能だった「第二種農地」から原則転用できない「第一種農地」に変更されていた。
その制約を取り払ったのが、地域未来法だった。
企業側との交渉などを担当した高岡市産業企画課の多嶋俊輔係長は「私たちはやはり企業の事業を進めたいし、企業が挑戦できる環境を整備するのも行政の役割と考え、あの手この手を検討した。結局、たどり着いたのが地域未来法だった。企業の申請から開発まで1~1.5年と、スケジュール感がある程度見えるのも利点だった」と振り返る。
高岡市は富山県と連携して、県による「重点促進区域」の設定、高岡市による「土地利用調整計画」の策定、企業側による「地域経済牽引事業計画」の作成と、地域未来法に則った調整、手続きを進めた。その結果、「第一種農地」から産業用地への転用がスムーズに進み、リーマン・ショックからこの間、吹いていた逆風をはねのけることができた。
高岡市産業企画課の今方順哉課長は、「企業がこの地で生産活動を続けることは市の発展にもつながる。産業振興、さらに地域の持続可能な発展の面からも、地域未来法の活用は非常に有効な手段だ。今も多くの企業から用地取得の相談を受けており、地域未来法の活用を含め支援に取り組みたい」と語る。

企業立地を積極的に支援したいと話す高岡市産業企画課の今方順哉課長
地域未来法によるこうした産業用地の整備は、宮城県涌谷町、茨城県筑西市、福井県永平寺町など、全国各地で進んでいる。また、佐賀県鳥栖市など、同法を活用し、自治体と民間事業者が連携して、産業用地整備に取り組む動きも出てきている。
脱炭素、デジタル化――。高まる投資意欲に用地確保間に合わず
地域にとっては今、企業立地のチャンスが到来している。脱炭素社会への移行やデジタル化といった転換期を迎え、新たな分野に参入しようと、多くの企業が投資意欲をかつてなく高めているからだ。
一般財団法人日本立地センターの調査によると、国内事業拠点に関する立地(新設・増設・移転)の計画を持つ企業の割合は増加傾向にあり、特に2020年度から大きく伸びている。2023年度調査では、「新規事業所の立地計画がある」とした企業は25.0%で、前年度比1.1ポイント増。3年連続の増加となった。特に、物流業(23.1%、前年度比1.0ポイント増)では2012年度の統計開始以降で最高となり、製造業(32.6%、同2.1ポイント増)はバブル期以降で最高の水準となった。

また、経済産業省が都道府県と政令市を対象にしたアンケート・ヒアリング調査(2023年8~9月実施)によると、「直近1年間で、立地を検討する企業等からの問い合わせが増加した」は62%に上る。
その一方で、企業等からの二―ズに応えられる工業団地を確保できている都道府県等は9%にとどまっているのが実情だ。
ガイドライン、基本方針改定でさらに柔軟かつ迅速化。自治体の企業立地を後押し
こうした状況を受けて、2023年、地域未来法に関する重要な見直しが行われた。
7月に基本計画のガイドラインが改定され、企業の立地計画がない段階でも、自治体が「重点促進区域」を設定できることを明確化した。これにより、早い段階から企業と自治体が向き合い、産業用地の整備に動くことを後押しする。
さらに12月には基本方針が見直され、市街化調整区域での開発許可の配慮の対象となる施設が拡充された。これによって、自治体が産業立地の促進に必要と認める区域であれば、市街化調整区域であっても、一定の条件を満たせば、工場や研究施設、物流施設の建築を目的とした開発許可が可能となった。地域の事情に応じた産業立地を、より柔軟かつ円滑に進められることが期待されている。
経済産業省は、地域未来法の積極的な活用を促している。今後は自治体向けに「産業用地整備ガイドブック」を公表するなど、伴走支援を充実させることで、産業用地を確保したい企業のニーズに応え、自治体の企業立地戦略を手厚くサポートする方針だ。
【関連情報】
地域未来投資促進法(METI/経済産業省)
土地利用転換の迅速化に向け、地域未来投資促進法の基本方針を改正しました(METI/経済産業省)