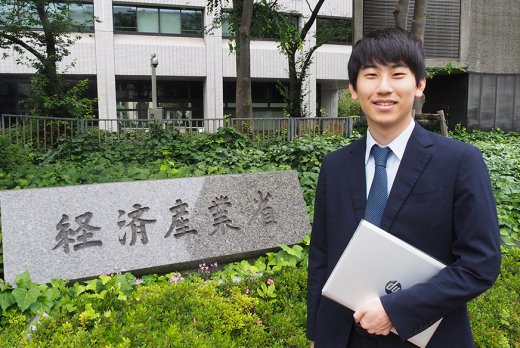”なるほど!”が集まるウェブマガジン
スポーツ産業が地域を盛り上げる
我が町のチームが求心力に

広島東洋カープが昨年、25年ぶりにセ・リーグ優勝を果たし、一大旋風を巻き起こしたように、スポーツほど地域を盛り上げるものはない。プロチームの存在は、“ホームタウン”の住民の求心力として働き、スタジアムは集客拠点として交流人口の拡大につながる。もちろん経済効果も小さくない。スポーツの産業化から地域の未来を見てみる。
全国で最速の人口減少
少子高齢化の影響が大きい東北地方にあって、より深刻なのが秋田県だ。全国で最も速いペースで少子高齢化が進み、今年4月には東北で唯一、人口がとうとう100万人を切ってしまった。しかし、そんな逆風をモノともせず、リーグでもトップクラスの集客力を誇るプロスポーツチームがある。男子プロバスケットボールのBリーグに所属する、秋田ノーザンハピネッツのことだ。
あきたにはBがある
「あきたにはBがある」。そんな合言葉の下、秋田ノーザンハピネッツは地元から熱烈な支持を集める。ホームタウンは秋田市を中心とした県全域。2016年発足のBリーグでは、初年度の2016-17シーズンに9万人の来場者数を達成。全36クラブ中4位の集客力を誇る。10代以下の子どもから60代以上の高齢者まで幅広い世代に浸透する。
運営会社の秋田ノーザンハピネッツは2009年の設立。bjリーグの2010―11シーズンから参戦している。同社を率いるのが水野勇気社長。留学先のアメリカとオーストラリアで見たプロスポーツチームのあり方が、原点となった。これらの国では町ごとにスポーツチームが存在し、エンターテイメントとして地元の人々を楽しませていた。そのような地域の拠り所となるようなスポーツチームを秋田でも目指した。

水野社長自身は東京出身だが、秋田市内にある国際教養大学に進学したのを機に移住。ただ秋田県は「どこか元気がない」という印象を持っていた。そんな地域を活性化するのがスポーツ。留学時に抱いた「スポーツを通じて地域に新しい楽しみを提供できるのではないか」という気持から、帰国後は秋田初のプロスポーツチーム立ち上げに奔走した。
秋田には高校バスケの強豪も
秋田県と言えば、やはりバスケットボールだろう。全国優勝タイトル数が高校最多の58回という、高校バスケットボールの圧倒的な強豪、能代工業高校はあまりにも有名だ。地域には古くからバスケットボールを愛する土壌があり、雪深い冬季も活動でき、集客を見込める屋内スポーツというのも好都合。秋田県でスポーツチームを立ち上げるとしたら、バスケットボール以外にはありえなかった。
日本のプロスポーツでは野球、サッカーと比べまだまだマイナー感があるバスケットボールだが、秋田県に限っては「地元でのチームの知名度は9割を超える」(水野社長)。もちろん新たなファンの取り込みに向けた地道な広報、地域貢献活動も欠かさない。地元紙やローカル局とのつながりを重要視し、選手のメディア露出を増やしているほか、選手やスタッフを地域の小学校や祭り、スポンサー企業のイベントなどにも派遣。地域住民と直接ふれあう機会を大切にしている。今年の7月末に県内が記録的豪雨に見舞われた際には、床上浸水の被害を受けた家屋の土砂を取り除くボランティア活動にも取り組んだ。

今期の目標は10万人動員
B1リーグで戦った昨シーズンは残留プレーオフで敗れ、今年9月末から始まるシーズンは2部リーグで戦うことになる。水野社長は「まずはB2リーグで優勝し、1年で昇格する」と力を込める。
Bリーグが掲げるリーグの使命の一つに「エンターテイメント性」がある。「勝つことはもちろん重要。ただ、負けたとしても『楽しかった、また来よう』と思わせる会場づくりをすることが大切」と水野社長は説く。「昨シーズンはなかなか勝てなかったが、集客は伸びている。このまま集客を減らさず成長し、今シーズンは年間10万人の動員を目指す」(同)。すでに秋田県では欠くことができない存在となっている。
球場ではなくボールパーク
もはやスタジアムは、試合を観戦するだけの場ではない。そこに商機を見いだしているのが三井物産グループだ。広島カープのホームグラウンドであるマツダスタジアムが2009年シーズンに開場してから、スポンサーシップマーケティング業務、フードサービス業務、球場内一部清掃(選手用ロッカーなど)を請け負っている。「球団にとって重要な収益源であるスポンサーシップやフードサービスを、当社グループのネットワークや専門性を活かすことにより最大限サポートし、球団にはチーム運営により特化してもらえるよう尽力したい」と、三井物産サービス事業部の川島康敬マネージャーは説明する。

三井物産グループでフードサービス業務に実際に携わるのは、米アラマークとの合弁会社で、給食サービスなど中心に事業を展開するエームサービスだ。球場のフードサービスを包括的に運営することで、球団と一体となり、マツダスタジアムでしか味わえないメニューを展開するなど、広島東洋カープの人気を支えている。
マツダスタジアムのフードサービスの最大の特徴は、球場内にある29の店舗を、全てエームサービスが運営している点だ。山村俊夫社長は「他の球場はテナントが各店舗を運営しているが、マツダスタジアムはメニュー開発もエームサービスがやっている」と話す。エームサービスでは、マツダスタジアムに調理師を含む約90名の調理スタッフを配置し、メニューを開発に力を入れる。
30選手とコラボメニュー
選手とのコラボレーションメニューでは、春のキャンプから選手と打ち合わせを重ね、オリジナルの商品を開発。他のチームでは一部の人気選手のみに限られることが多いが、マツダスタジアムでは、シーズン中に何回か入れ替えながら、30選手分という1軍のほぼ全選手のメニューを提供している。

また、広島の特産物である「藻塩」を生かし、地元小学生考案のメニューを商品化したり、うなぎの代替食材として、なまずの養殖を研究する広島県立油木高校のなまずを使用したメニューを開発し、期間限定で販売するなど、地域との共生に取り組む。
全ての店舗を管理していることは、運営面でもメリットが大きい。球場では、開場から試合半ばは食事をする観客が多く、デザートであるスイーツが売れるのは、どうしても終盤になる。エームサービスは観客の動向を的確に捉え、販売員の配置を時間ごとに変えている。こうした運営上の工夫は、全ての店舗を包括的に管理しているからこそ可能となる。
国内唯一のコンコース
マツダスタジアムは飲食などの店舗が並ぶコンコースを、座席の区分に関係なく、歩き回ることができる。たとえば、多くの球場は1塁側から3塁側に入ることはできなかったり、内野と外野も区切られている。必然的に、売れ筋となる麺類や丼物など、同じようなメニューを扱う店舗ばかりが並ぶことになる。しかし自由に歩き回れるマツダスタジアムであれば、店ごとにメニューを変えることができ、ファンはバリエーションに富んだ料理を楽しめる。こうした設計の球場は米国では多いが、日本ではマツダスタジアムのみで、店舗運営において、大きな優位性になっている。
2000年代初めに、広島市の新球場建設計画が浮上。これを受け、当時は三井物産に在籍していた山村社長が球団にフード業務の事業構想を提案。この中で強くアピールしたのは「球場の飲食の概念を根本的に変える」ことだった。日本では男性中心のプロ野球に対し、米国で球場は「ボールパーク」と呼ばれ、世代や性別に関係なく野球を楽しむ文化がある。女性客を意識したスイーツの店舗を充実させるなど、フード業務を通じてファンの幅を広げることにも注力。こうした戦略は「カープ女子」と呼ばれる女性ファンの拡大にも寄与しているはずだ。

チーム成績の背景にはスタジアム改革?
大リーグのようなボールパークを目指し、スタジアム改革で先頭を走る広島カープ。三井物産は、その改革を裏側から支える立場になった。「新球場開設という希少な機会に恵まれた」と川島マネージャーは話す。マツダスタジアムが開場するまでは、広島カープの観客動員数はセ・リーグで最下位が定位置だった。それが2015年に初めて200万人を突破し、優勝した2016年も増加。今シーズンも1試合平均で3万人以上動員し、昨シーズンのペースを上回る。スタジアム改革が観客を増やし、それがチーム成績に好影響を与え、さらに観客が伸びている。
2020年の東京五輪・パラリンピックだけでなく、今後Bリーグで5000人規模のアリーナ建設が動き出すように、国内では新たなスポーツ拠点の整備が加速しそう。そこで重要となるのは試合への集客力だけでなく、限られた試合日以外の稼働率をどう高め、地域に根ざした施設にしていくか。「施設運営の知見をもっと得て、単にスポーツが行われる場でなく、地域の人々が集い、地域の活性化につながるような場とするオペレーターになりたい」と川島マネージャーは意気込む。スポーツの産業化には、裏方のプロフェッショナルの存在も欠かせない。