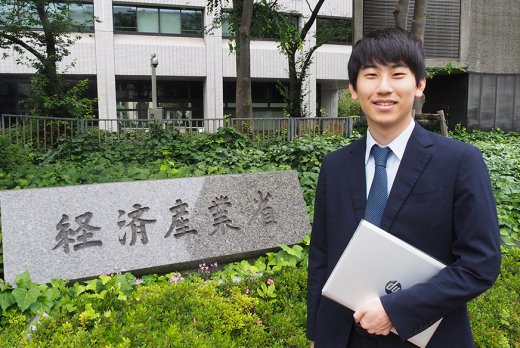”なるほど!”が集まるウェブマガジン
大手企業も組織の枠を超え、連携を模索
横つながりでイノベーション加速

「多様な視点」こそ企業の競争力。そんなダイバーシティ2.0の時代に、女性を女性向け商品の開発やダイバーシティ推進の関連部署に従事させるといった取り組みだけで良しとしていては、とてもじゃないがこの先、グローバル競争に勝ち残ってはいけない。どれだけ多様な人材を企業の枠を超えて巻き込んでいくことができるのか、多くの企業が模索し始めている。
日本最大級のモノづくりコミュニティ
「企業や組織を介さずに、アイデアや技術を持つ人たちが集まって何かを作る場があったらいい。そう考えて、『Wemake(ウィーメイク)』をつくりました」と、大川浩基さんは話す。Wemakeは、日本最大級のウェブ上のモノづくりコミュニティー。エンジニアやデザイナー、建築家、主婦などさまざまなバックグラウンドを持つ1万人以上の“つくりたい人”と、企業とを結びつける。大川さんは、Wemakeを運営するA(エイス、東京都港区)の共同代表を務めている。
Wemakeは個人が参加するコミュニティーとして2013年に立ち上がった。商品化を目指す企業を巻き込む、現在の形になったのは2015年から。仕組みはこうだ。企業は社内にないアイデアやリソースの拡大を求めて、Wemakeの参加者から新商品などのアイデアを募る。参加者は、「あったらいいな」と思うアイデアをコミュニティーに投稿する。
コミュニティー内の他の参加者も、投稿に対して改善案や意見などを出す。さまざまな経験やバックグラウンドを持つ人たちの多様な視点を通すことで、アイデアをより磨くことができるというわけだ。投票や審査を経て絞り込まれた最終案は、マーケティングや販売戦略まで練られる。アイデアの完成度が高いため、企業はスピーディーに商品化へ動き出せる。
中小企業とのプロジェクトも
Wemakeでは、平均して4、5プロジェクトが並行して進む。ダイキン工業や富士ゼロックスといった大手企業だけでなく、高度な金属加工技術を持つササゲ工業(新潟県長岡市)や、JR九州の高級寝台列車「ななつ星」に照明用LED導光板を納入したワイ・エス・エム(埼玉県八潮市)といった、技を持つ中小企業とのプロジェクトも始まっている。
一つのテーマに対し、集まるアイデアは100から200。3Dプリンターでプロトタイプをつくる参加者さえいる。商品化が決まれば、ロイヤリティー収入というリターンはある。そうはいっても、参加者はかなりの労力をかけている。
商品化へのモチベーション
ゼロから何かを創り出す。そんな労力も時間もコストもかかる段階を、Wemakeに担ってもらえるため、企業側のメリットは大きい。参加者の中には大手企業のエンジニアもいる。大きな組織で担えるのは、商品化のプロセスのほんの一部に過ぎない。しかしWemakeでは、自分次第でプロジェクト全体に関われる。加えて、普段の仕事では知り合うこともできない異分野の優秀な人材や、北海道と九州というような遠く離れている人と一緒に仕事ができるのも参加者にとっての魅力となっている。
モノづくりのスキルを持ちながら、子育てなどで仕事を離れた主婦。自分の知識や技術を使って、「腕試しをしたい」という人。IT業界などでは、企業の枠を越えて集まるイベントも珍しくないが、製造業では珍しい。しかし「そこには必ずリターンがなくてはいけない」と、大川さんは強調する。「自分が関わったものを商品化したい」との思いが、参加者の最大のモチベーションになっている。だから企業に対しては「展示会で発表するコンセプトのような話はお断りしている」(大川さん)。
運営工夫し、最後まで熱を上げたままで
類似したモノづくりコミュニティーは過去にもあった。2015年に倒産した米Quirky(クワーキー)は、ピーク時には100万人以上が参加。週に新商品を3種類発売し、クワーキーで得たロイヤリティー収入をもとに起業する成功者も現れた。大規模化していく間に、あまり売れない商品や、収支バランスの悪い商品も増え、最終的には失敗に終わった。だが、クワーキーの存在は、プロジェクト単位で人がつながれば、社会に企業とは違う新しい価値を提供できることをはっきりさせた。
Wemakeでは、「最後まで参加者や企業の熱を上げたまま進むように、コミュニティー運営を工夫している」(大川さん)。アイデアを募集した企業からも少なくとも1人の担当者に初期段階から参加してもらう。商品化する際の考え方と離れてしまわないようにするためだ。
プロジェクトの中には、最終的に企業からの参加者が数十人に増えたものもあった。企画やマーケティング、製造、営業などさまざまな部門の人が参加すれば、商品化がよりスムーズに進む。そんなつながりが、他のビジネスでも活きる可能性もある。
A(エイス)のオフィスに足を踏み入れると、壁の一角にびっしりと貼られた付箋に圧倒される。運営面の改善やロードマップなどが、一つ一つの付箋に書き込まれている。ウェブ上のネットワークを使うデジタル化の最先端のモノづくりも、昔と同じそんな熱意に支えられている。
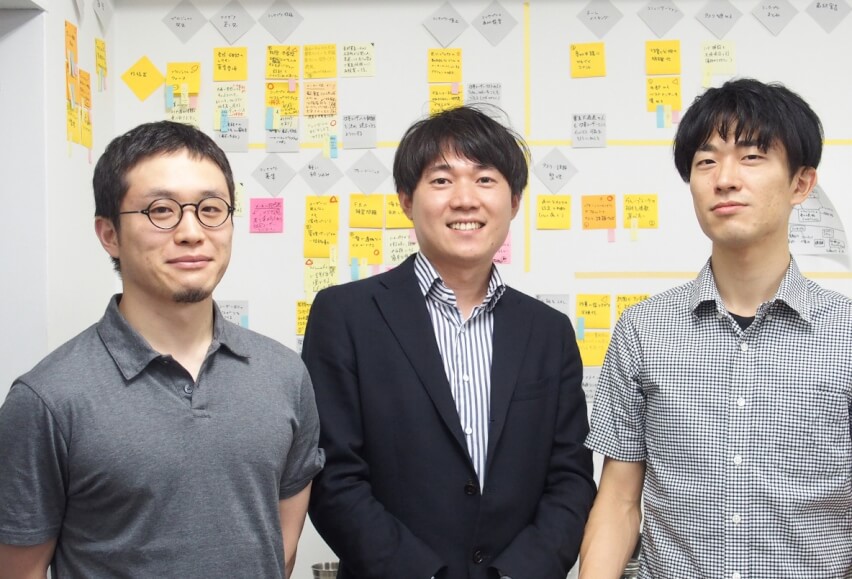
社会起業家と企業を結ぶ
渋谷駅から坂を登った先にあるNPO法人「ETIC.(エティック)」(東京都渋谷区)のオフィス。そこには若い起業家や起業家の卵が集まり、活発に議論していた。エティックが取り組むのは、社会起業家の創業・成長支援や、大企業との橋渡しなど。ソーシャルイノベーション事業部マネージャーの佐々木健介さんは、「社会起業家やNPOとの連携は、企業にとってダイバーシティの新しい段階になる」と話す。
利益を目的とする企業に対して、NPOは課題解決を目的とする。大企業は失敗しないようにA案、B案、C案と用意するが、社会起業家は稼げるかどうかわからないものに人生をかける。「初めてNPOの人に出会った大企業の人は驚くが、『支援してあげる』姿勢でなく、違う専門性を持つ人として尊敬して関係をつくれば、新しいものを生み出せる」と佐々木さんは話す。
エティックと連携する大企業の中には、東北の農家を対象としたNPOによる復興支援の一環で遠隔管理技術を開発し、その技術の海外展開を検討し始めたところもあるという。「本気で関わることで、新しいビジネスにつながった事例だ」(佐々木さん)。

大手企業も社会課題の解決に関心
東日本大震災以降、企業がCSR活動の一環として社会課題の解決に向き合う事例が増えてきた。かつての好景気を背景としたメセナ活動と違い、社会課題の解決は、企業の広告宣伝として行うには大きな負担となる。それでも、「本業の社会的価値を問い直すため、関心が高まっている」(同)という。現在、NECや花王、NTTドコモ、電通などさまざまな業種のさまざまな企業がエティックと連携している。
エティックから支援を受けて起業した事業は、LGBTの理解促進や、駅前血液検査による予防医療、農業支援、介護など多岐に渡る。そのいずれもが、もともとは営利事業として成り立たちにくい課題だった。「こうした課題を解決するには、個人の思いに加えて、いろいろな人を巻き込む必要がある」と佐々木さんは話す。
社会課題の解決も、多様な人材と手を携えるダイバーシティがカギとなる。佐々木さんは「NPOは、企業がやれない領域を先んじて研究開発している。それを大きくできるかは、企業がどういった姿勢で関わるか次第だ」と指摘する。さまざまな業種で事業を取り巻く環境が変化している今、NPOや社会起業家は企業にとって「次のステージへ進むパートナー」となり得る。先進的な企業は始めつつある。