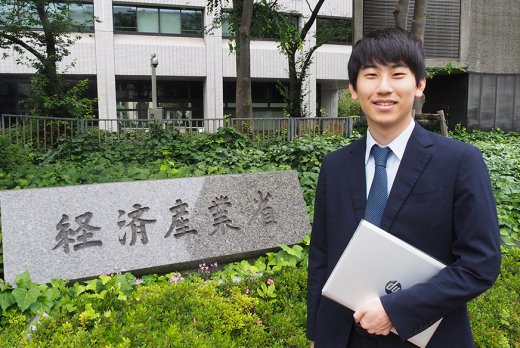”なるほど!”が集まるウェブマガジン
【北海道発】水野染工場は進化を続ける染物屋。テーマパークも開いた!
水野染工場 北海道旭川市
生地織物に文字や記号などの「印」を付ける「印染(しるしぞめ)」。くっきりと染まることから、遠くからでも図柄が一目で分かる。戦国時代には、いくさのときに敵味方を区別するために家紋を染め抜いた幟(のぼり)として使われたと言われる。
現代でも、祭りなどで着る半纏(はんてん)や、店ののれん、大漁旗などで独特の風合いが愛されている。ただ、ライフスタイルの変化や安いプリンターの普及などにより、第2次世界大戦前に国内には1万4000ほどあった印染業者は、現在は250ほどに減っているという。
こうした伝統産業にあって、独自の進化を遂げているのが水野染工場である。東京都内に店舗を開くなど挑戦に挑戦を重ね、ついには、北海道内に藍染めのテーマパークも開いた。水野染工場とはいったいどんな会社なのか――。
職人の勘頼みから脱却。CADやネット販売もいち早く導入
水野染工場の創業は1907年。知人から「紺屋がなくて困っている」と誘われ、初代・水野竹治郎氏が富山から旭川に移り住んで、事業を始めた。清流に恵まれた旭川は染め物の適地でもあった。
現社長の水野弘敏氏は4代目となる。1986年に入社した当時の水野染工場は、両親と3人の職人で仕事を回す零細な町工場で、家業に入る際には迷いもあった。ただ、大学生時代に大型スーパーでアルバイトをしたときのこと。大企業ではどんなに成果をあげても、給料は少ししか上がらなかった。「小さい会社ならば、僕が2倍働ければ、給料も2倍になる」と考えたという。
世の中はバブル景気へと突入していく。しかし、水野染工場は給料の支払いに苦労するほど、火の車だった。「入ってすぐに、これはまずいと思いました」と振り返る。
そこで、取りかかったのが、工程のマニュアル化である。染め物では、顧客から指定された色を表現するためには、様々な染料の配合比率がカギを握る。ただ、職人の勘が尊重され、その勘も“見て覚える”のが当然の世界だった。
水野氏は、色を作るごとに、染料の配合比率をファイルにまとめた。色見本のサンプルが300種を超えると、始めは無視されていた職人から、色の作り方を聞かれるようになった。
さらに、工場を狭い街中から郊外の国道沿いに移転するとともに、CAD(コンピューター支援設計)システムの導入などIT化を進めた。生産効率はどんどん改善していった。
一方で、青年会議所(JC)などの活動を通じて人脈を広げ、イベントなどで生じる祭り用品の需要を着実に取り込んでいた。中小・零細企業としてはかなり早く、1998年にはネット販売を開始した。
東京・浅草に「染の安坊」出店で大勝負。苦戦のワケは?
40歳を過ぎて、水野氏は大きな賭けに出た。
印染業界では受注販売が常識だった。注文が集中する夏から秋に合わせて、設備や人材をそろえると、閑散期には余剰が生じて採算割れになるため、仕事を断らざるを得ない。これが企業として成長できない要因になっていた。
受注に頼らない既製品を作ったところで、きちんとした販路がなく、安く買いたたかれてしまうのが関の山だった。「失敗しても60歳までには取り返せる。60歳になってから、あの時にやっとけばよかったと後悔はしたくない」と強く思った。
旭川・札幌間を特急列車で行くのも、旭川・東京間を飛行機で行くのも1時間半程度とほぼ変わらない。どうせなら、人ができるだけたくさん集まる場所にしようと、2004年に子会社「染の安坊」を設立し、東京・浅草の雷門の近くに、直営店を出店した。その時点の年商約1億2000万円に対し、投資額は約3000万円に上った。
意気込みに反して、売れ行きはさっぱりだった。顧客が指定した図柄を作る受注生産と異なり、小売りの世界では、自らが売れ筋を生み出していかないといけない。「こうすればかっこ良さそうだから、作ってみよう」という感覚頼みの商品づくりは通用しなかった。
ツテをたどって、著名なデザインの専門家に頭を下げた。図柄や色使いなどを一から勉強させてもらった。店頭で美しく見せるためには、売れない色もそろえる必要があることなども学んだ。商品改良の結果は次第に現れていった。中でも、あまり期待していなかった手ぬぐいが看板商品になった。従来品よりサイズを大きめにして、特岡というキメの細かい布に変えたことが奏功した。
巡音ルカ、ソメスサドルなどとのコラボ商品でも快進撃。米国で感じたある変化
水野染工場は、時流に合わせて、先進的な手法を積極的に採用している。2007年には生産管理システムを導入。現在では、顧客からの発注内容をタブレットで管理し、社員で共有する仕組みを作っている。少ない注文であっても短い納期で商品を届けることを可能にしている。
人事面では、360度評価を導入している。社員同士は全員が順位を付けて評価し、集計結果を賞与や昇進・昇格の基準に反映させる。水野氏は「大企業なら、気に入らない上司もそのうち代わる。そうならない中小・零細企業では、部下も上司を評価できるようにするべきなのです」と話す。
商品の評価が確立されると、次から次へと新たな商機が舞い込んできた。人気バーチャルシンガー「巡音ルカ」をあしらった手ぬぐいや、日本唯一の馬具メーカー「ソメスサドル」と共同開発したバッグなど、様々なコラボ商品を販売した。染の安坊は米国のファッションブランド「Supreme(シュプリーム)」に手ぬぐいを納入する機会も得た。
2020年には、東京都心に新たに「日比谷OKUROJI店」をオープン。2021年の東京五輪の開会式では、染の安坊が納品した半纏をまとった消防団が登場した。
日本らしさを感じさせる商品だけに、海外展開にも力を入れている。2017年以降、タイ・バンコク、フランス・パリ、米国・NYなどでの見本市などにたびたび参加している。バンコクでの販売会では用意していた手ぬぐい135本が1時間で完売した。
ただ、米国での見本市では時代の曲がり角を迎えていることを痛感させる出来事もあった。安くはない料金を支払って出展したものの、会場は閑散としていた。「この状況をもたらしたのが、ネット通販です。おかげで、米国ではどんどん家族経営のパパママショップがつぶれているのです」。日本から毎年来ていた社長の言葉が水野氏の胸に響いた。モノを作って、売る。これだけでは、企業を永続させるのは日本でも難しくなると考えた。
美瑛町「藍染結の杜」でコト消費の場を作る。事業再構築補助金を活用
水野氏の出した答えが、「藍染結の杜(あいぞめゆいのもり)」である。本社がある旭川市の南隣の美瑛町で、十勝連峰を望むなだらかな丘の一角に、2022年にオープンした。
藍染結の杜は、“藍染めのテーマパーク”をうたう。水野氏は「ここで売っているのは体験の価値です。モノ消費ではなく、コト消費を盛り上げていくことは、地域の活性化にもつながると期待しています」と話す。
目玉としているのが、藍染め体験である。東京・日比谷の店舗や、海外の見本市などでも手掛け、好評を博してきた。布を小さく丸めて、紐でぐるぐる巻きにしてボール状に縛る。藍の染料に入れてから、水で洗う。布を取り出し、空気に触れさせていると、布は模様を映し出しながら深い青色へと鮮やかに染まっていく。誰でも気軽に自分だけのオリジナル作品を作ることができる。
また、カフェでは、藍を使った茶や、藍を使ったクッキーやケーキなどのスイーツなどが提供されている。敷地周辺には藍が植えられ、秋には収穫も楽しめる。ショップでは、職人たちが作った手染めのシャツや手ぬぐい、半纏などがずらりと並ぶ。まさに「藍」尽くしになっている。

藍染結の杜で提供される藍を使った茶。写真の水野里紗氏は、水野社長の次女で、後継者として修業中
美瑛町は絶景で知られるが、観光客が撮影のために農家の畑の中に無断で立ち入り、トラブルになるケースが出ている。藍染結の杜では、施設裏手にある「青の丘」に登って、思い思いの写真を撮れるのも、観光客にとってはうれしいポイント。国内外からのたくさんの観光客が、大自然の中でゆったりとした時間を過ごしている。
長く温めていた藍染めテーマパーク構想の実現を後押ししたのが、経済産業省の事業再構築補助金である。藍染結の杜の建物はもともと美瑛町が農産物の直販所として整備したが、水野染工場は土地を美瑛町から無償で借りたほか、建物の改装や設備の導入などに約7500万円を投資した。このうち約4000万円分については事業再構築補助金を充てている。
水野氏はこう語る。「半纏やのれんといった商品は、ニッチとして今後も世の中からなくなることはないでしょう。規模拡大を目指すのではなく、市場が小さくても、生き残れる”強い会社“になっていくことを目指しています」
【企業情報】
▽公式サイト=https://www.hanten.jp(水野染工場)https://www.anbo.jp/ ( 染の安坊)https://biei.blue/(藍染結の杜) ▽社長=水野弘敏 ▽創業=1907年 ▽社員数=20人(正社員)